義務教育をどうすべきか② @城陽市寺田にある個別指導塾 勉楽個別 寺田小・寺田西小・寺田南小・今池小・富野小・深谷小・久世小・久津川小・古川小・城陽中・西城陽中・東城陽・北城陽中・南城陽中・南陽高・城南菱創高・莵道高・久御山高・城陽高
みなさん、こんにちは。
京都府城陽市寺田にある個別指導勉楽個別です。
本日もブログを読んでくださりありがとうございます。
「義務教育をどうするのかシリーズ」の2回目となります。
実は、書いては直しをしております。
「これを書けば悪口に聞こえる」「このことを書けば一部への影響が大きくなる」
そんなことを考えていると書けなくなってしまいます。
なので「私見」としていることをご理解ください。
整合性がとれていない
現在、学校教育ではタブレットや教室でもテレビモニターを用いた授業が主流です。
その為、教科書を利用することや板書を書くことも少なくなっています。
その為、授業では「書くこと」や「内容を理解しまとめること」が極端に少なくなっています。
また、提出物の一部もタブレット上でタッチペンで取り組み、スクリーンショットで提出します。
その為、実際に問題を解く回数も少なく、内容も軽くなっています。
言い換えると、量も質も十分ではない状況です。
一方で、定期テストも受験も実際には「紙での実施」です。
また、必要な図、グラフ、補助線は勿論、文章を書くこともこれまでと同じように求められるのです。
そうすると、「普段の勉強内容」が「本番で十分活用出来ない内容」になってしまっているのです。
言い換えると「ダブルスタンダード」になっているのです。
何故そうなったのか?
この理由は、コロナ禍による速過ぎた世の中の変化も大きな理由です。
しかし、最も大きな理由は「欧米の模倣」だと私は思います。
日本としての目的や理念があれば良いのですが、そうではありません。
しかも、欧米諸国の中には「タブレット学習」「ITC教育」を廃止し、アナログ教育に戻っている国も出てきています。
先に書いた「質と量」の話にも関係するのですが、ITC教育は「軽過ぎる」と思います。
誤解を恐れずに書くと、現代の「ITC教育」「AI活用」や過去の「機械化」「オートメーション化」は「人手不足」からきています。
男女雇用機会均等法や定年年齢の引き上げ、外国人労働者の活用もそれが原因です。
言い換えると、「超少子高齢化」が諸問題の根底にあるのです。
これに関しては、既に「機を逸した感」が強く、政府の取り組みも全く効果が出ていません。
「子は宝」と言いますが、現状では「宝だからこそ刀のように鍛錬する」のではなくなりました。
大切に箱に入れてしまい込んでしまうイメージでしょうか。
また、オーストラリア、フランス、アメリカの一部の州等では、SNSの禁止や制限も行われるようになりました。
それが良いことかそうでないことなのかは判断が付きません。
しかし、子ども達の一日の生活時間の中の多くを占めているのは事実だと思います。
次回は、これらのようなことを書きたいと思います。
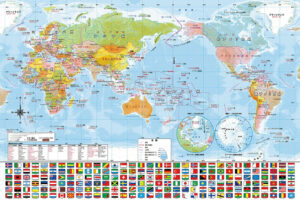
BEVERYより


